2024年1月12日
私はシステムエンジニアです。
稼働中のシステムに対して、新規の案件であったり、保守などで、システム構成の変更を行うことがあります。
その時にどこまでテストをするのか?という点を話たいと思います。
大前提として、変更したらテストする、という考えは変わりません。
では、どの範囲までテストをするか、は、毎回悩むところです。
テスト範囲を3つに分けると、このような感じ。
グレード1:最低限実施する
変更した部分が正しく機能するかインフラレベルで確認
グレード2:テストの前提は、まずこちらで考えたい
変更した部分を利用する業務処理を単体レベルで確認する
グレード3:できればより良い
変更した部分を利用する業務処理を結合レベルまで確認する
===
グレードの横にコメントを書きましたが、変更する機能の影響範囲で、どこまでテストをするのか決めることが重要。
限られた期間、限られた要員で変更からテストまでをしなければならない。
なので、全ての変更作業をグレード3まで行うのは遅延の原因になる可能性がある。
グレードの決め方は次の2つと考えている。定量的に評価はできないため、定性的に評価をしてグレードを決める。
・変更する機能が単純、複雑という視点
・システムに対しての影響度合い(例えば受注機能であればグレード3を行うべき)
===
テスト範囲を決めるのは正直難しい。
でも、変更作業をしてテストをしないのはありえない。
小さなテストでもよいからやる。
本日は以上です。
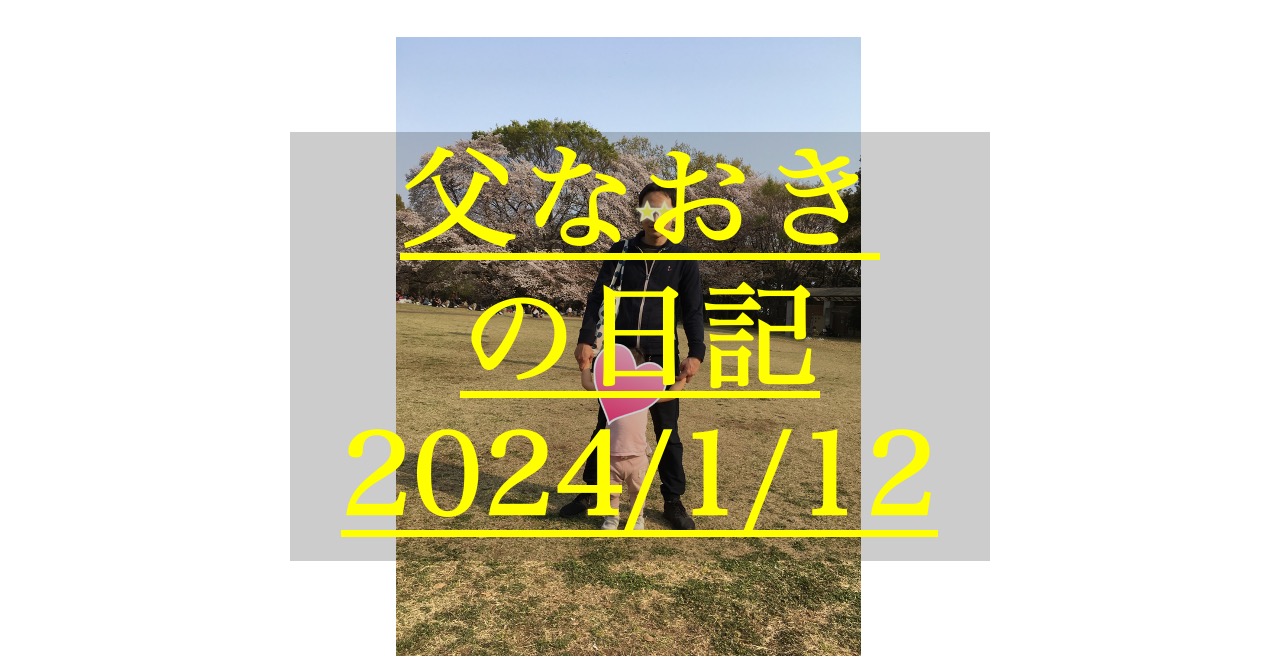
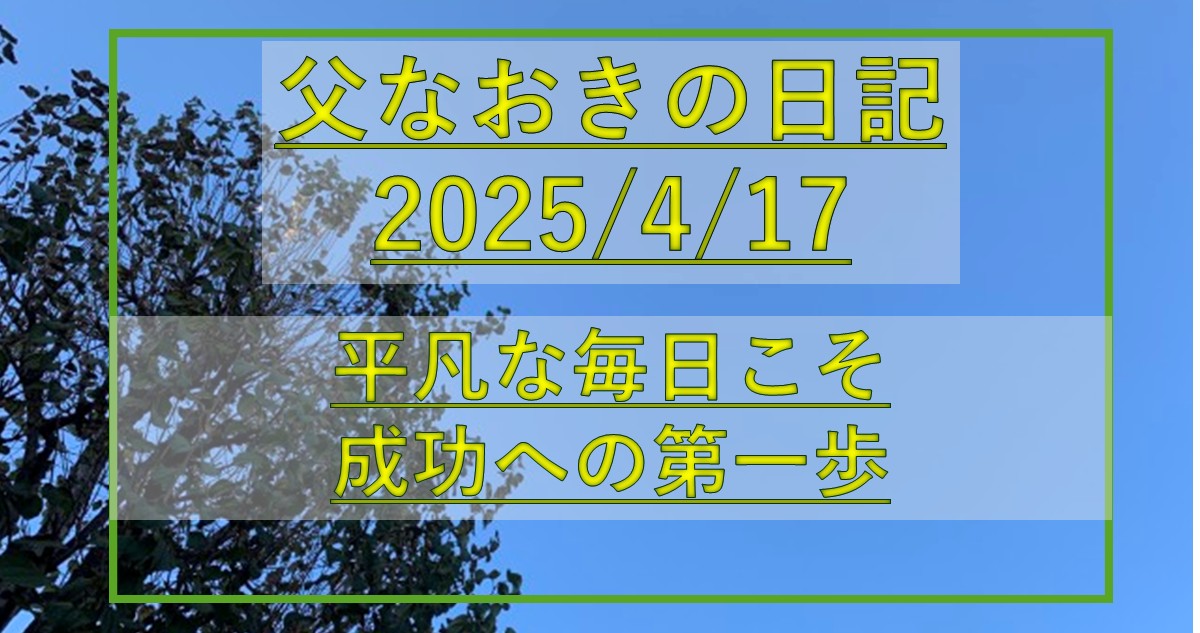
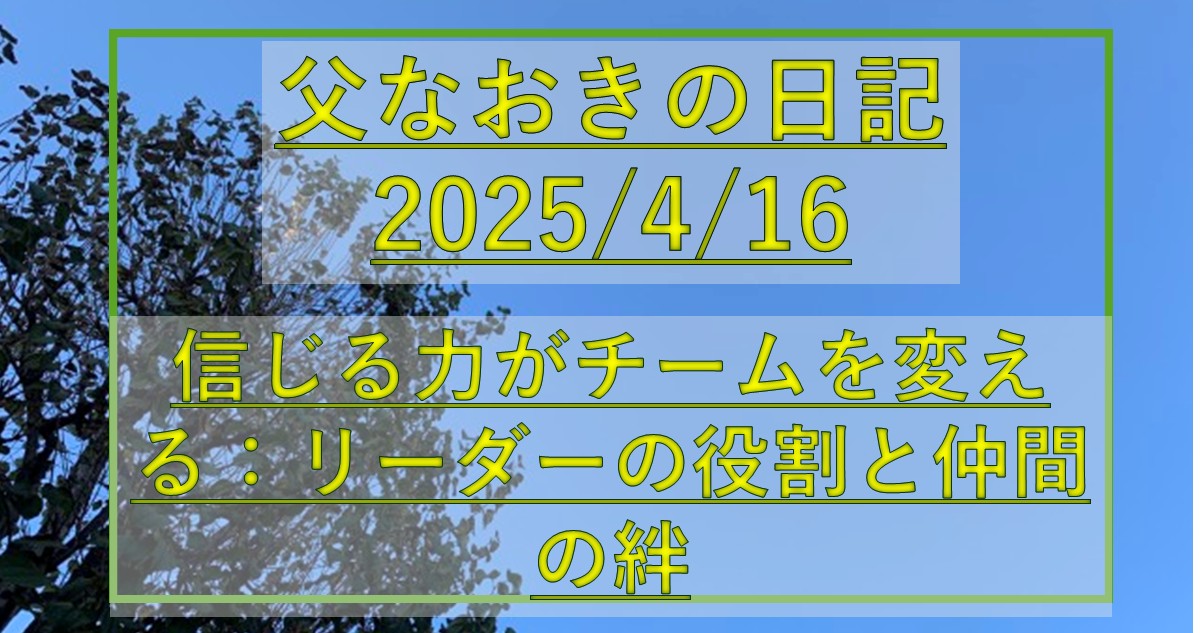
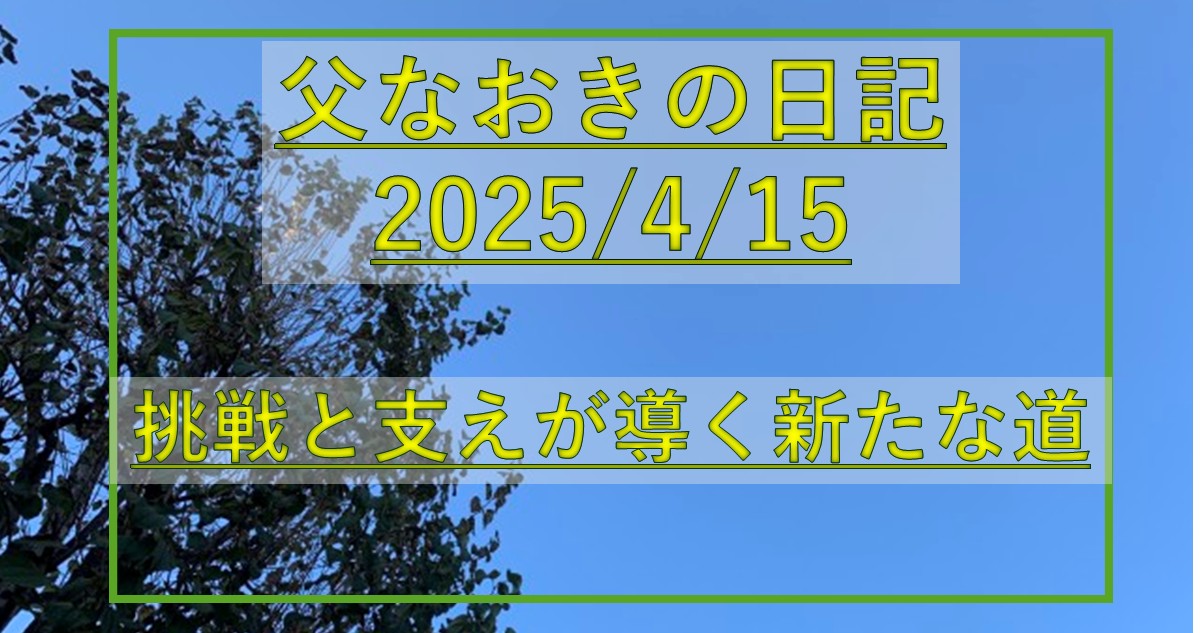
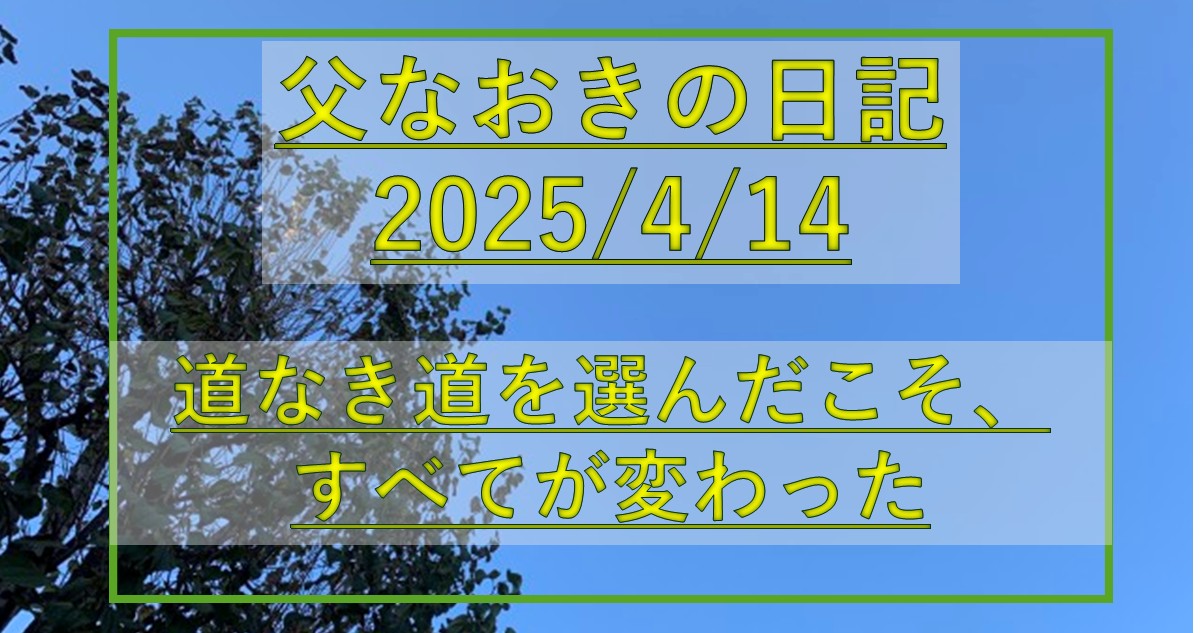
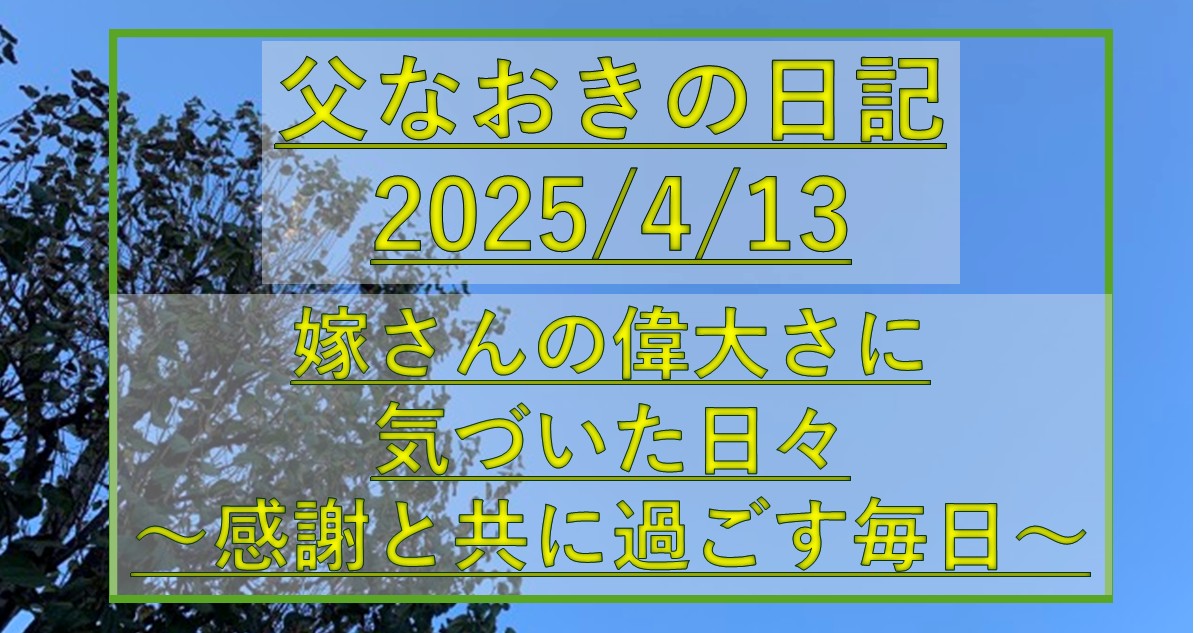
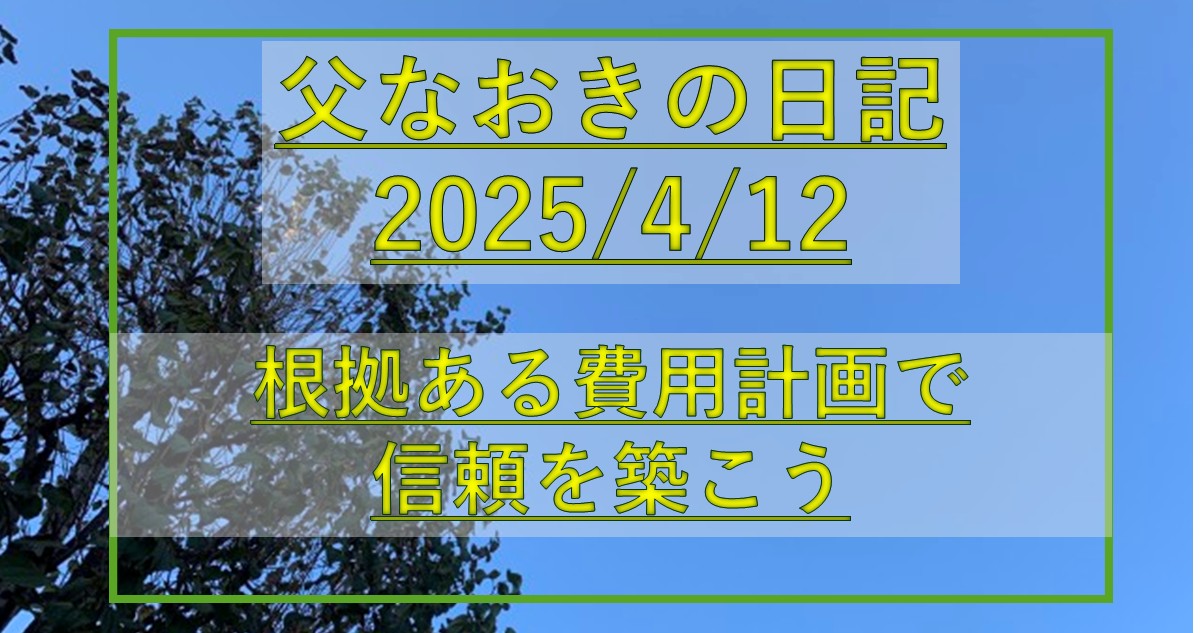
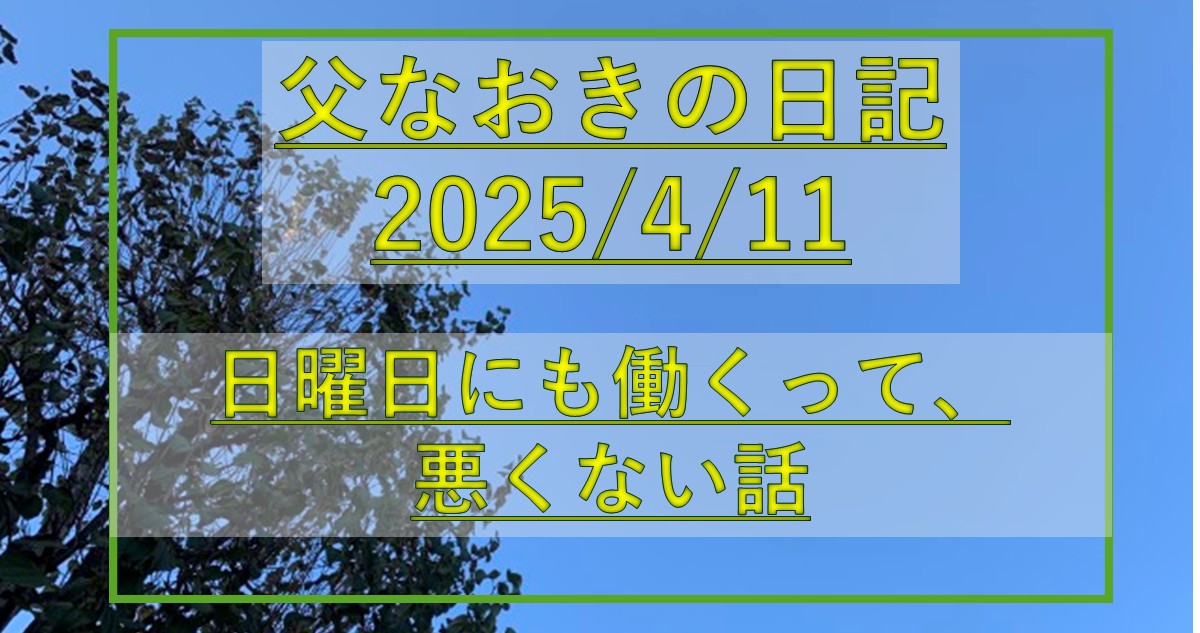
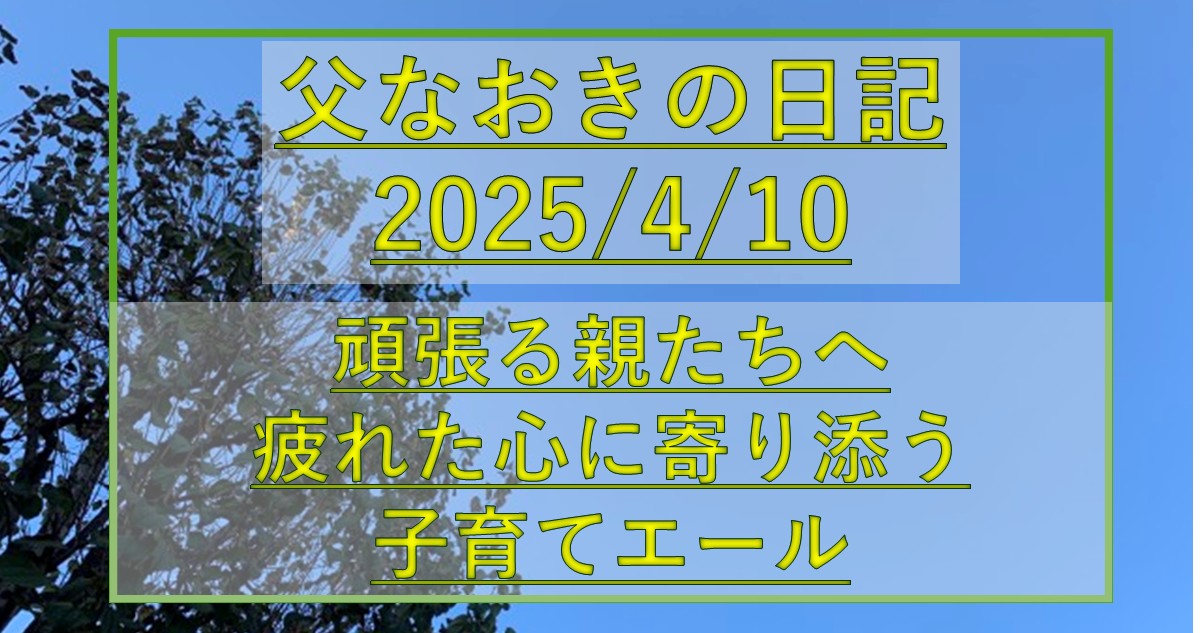
コメント